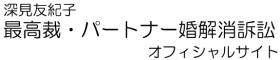星野豊「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について」に対する私のコメント
星野豊さんの文章は、控えめなのに力強く、精緻なのに温かいです。本件に関する論者の中では男女関係の本質を最もよく理解している方だと思いました。
「パートナー婚」という言葉
本件に関する論考のタイトルには、「婚姻外の男女関係」という語句が使用されていることが多いのですが、星野さんの論考のタイトルは、「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について」(As to the case of "the partner-marriage")です。「パートナー婚」というのは、従来の内縁および事実婚と本件を区別させるために、(このサイトを立ち上げる際に)私が名づけたものであり、彼も「かかる男女関係のあり方が従来の議論の中で想定されてきた男女関係とやや次元が異なる部分を含むものと理解する」ことから、「パートナー婚」を採用し、さらにタイトルにサイト名である「パートナー婚解消訴訟」を、英語タイトルにドメイン名である" partner-marriage"を使用しています。これは私にとって非常にうれしいことでした。 ((1) p.59 [*1])
「婚姻外の男女関係」という語句を使うと、論点がぼやけて何を言いたいのかよくわからない論考になってしまうと思いますが、不思議なことに、論者の多くはタイトルの重要性に気がついていません。
事実認定の緻密さ
星野さんは、事実認定を詳細に行っています(X=私、Y=裁判相手、Z=Yの法律婚相手 [*4] [*5] [*6] [*7])。
[*4] この点に関して、専らYの側から、金銭等のやりとりはもとより家事分担結果のメモに到るまでの詳細な書証が提出されている。後に三7で検討するとおり、このYによる立証活動が本件におけるXY間の関係の解釈のみならず、かかる関係の法的保護の必要性に関する判断についても、事実上影響を及ぼした可能性が高いように思われる。
[*5] この点に関して、第一審及び第二審では、Yの勤務先から配偶者の出産に関する補助金を受領する関係から、との理由が併せて認定されている。
[*6] この点に関し、第一審及び第二審では、出生前に多胎妊娠であることが判明したため、Xが人工妊娠中絶を希望したが、Yが人工妊娠中絶を承諾しなかったとの事実が、併せて認定されている。
[*7] 但し、同時に、例外的に、授業参観など、子供が希望した場合についてはXの負担とならない範囲で参加する、との取り決めもなされている。(以上、(1) p.63)
この緻密さに比べると、判決後まもなく出された水野紀子さん、石川博康さん、吉永和隆さん、本山敦さんたちの解説は極めて表面的です。彼らの解説は、最高裁判決を「速報」として紹介するという点に意義があるといわれるならばそれまですが、法律家が当事者の事実関係を深く調べることなく、一般市民よりも上の立場から「Xがどうの、Yがどうの・・」と評することに問題はないのでしょうか。
なお、[*4]は16年の「パートナー婚」期間中、裁判相手がいかに私に固執していたかを示すのに十分な証拠だと思います。
「バートナー関係」の破綻という認識
星野さんの次の一文を読んだとき、私は本訴訟において戦略を間違えたのではないかと後悔しました。事実婚の要件などといったものと比較することなく、独自に論破したならば勝てたかもしれないということに気づいたのです。
このように考えると、本件で問題とされたXのYZに対する慰謝料請求が認められるべきか否かについて考えるためには、本件が法律婚ないし事実婚とどの程度の相対的な親近性を有しているか、という観点からではなく、端的に、XY間において形成されていた個人的関係としての「パートナー関係」における何らかの秩序がYないしZによって一方的に破壊されたと考えられるか否か、そもそもXY間において形成されていたパートナー関係における何らかの秩序が、法律上保護するに値しないものであったか否か、という観点から、再検討する余地があるように思われる。((2) p.96)
法律婚=「秘密婚」
しかし、星野さんの論文を読み解いていくうちに、彼の提起する事柄はそれだけにとどまらないことがわかってきました。その一つの例として、法律婚は一種の「秘密婚」に近いものになり得るのではないかという指摘を挙げることができます。
[*18] この観点からすれば、内縁、事実婚を「法律婚に準ずるもの」と考えること自体も問題となる余地がないではない。すなわち、法律婚であるか内縁、事実婚であるかは、要するに夫婦関係の形成及びその正統性を社会の中で誰が認証しているか、という違いに過ぎない、という考え方にも説得力があるように思われるからである。そして、この観点をさらに進めるなら、国家をはじめとする各機関による個人情報保護の必要性が前面に出てきている現代にあっては、法律婚とは、国家による戸籍が法律上の正当性を以て回覧される範囲でのみ周知となる(当然のこの範囲にあってその事実を知った者については個人情報保護のための守秘義務が課せられる)という一種の「秘密婚」に近いものとなっており、それに対して内縁、事実婚とは、社会生活上の関係者に対して事実を公開してそこからの認証を受けるという一種の「社会婚」に近いものである、と捉えることも可能かもしれないわけである。(中略)いずれにせよ、このような観点から法律婚の現代的意義を考えてみることは、それなりに興味深いように思われるが、この点に関するより詳細な検討は、今後の課題とせざるを得ない。((1) p.73)
これまで、法律婚は社会的に承認されているという意味でオフィシャル=ノーマルであり、その他の男女関係については、法律婚からの距離によって、ほぼノーマル→ノーマルな要素が多い→かなりアブノーマル→完全にアブノーマルと、さまざまな段階が存在するという認識が主流でしたが、ここでは、法律婚が“シークネットなもの”になる可能性があるという、パラダイム・シフトが見られます。
「そんなこと、起こり得ない。」多くの人々がそう感じたとしても、未来は誰にも予想できないと思います。つい最近まで入籍前の「妊娠」は“赤っ恥”だったのに、ごくわずかな間に、「妊娠」は入籍への最強のスプリングボードになったではないですか。こういったシフトはなだらかに連続的に起こることは決してなく、突然起こるものです。
「個人主義」の徹底
次に私が驚いたのは、「パートナー婚」の特徴は「個人主義」をある意味で徹底させた男女関係を形成しようとした点にある、と見抜いたことです。
「本件におけるXとYとは、その居住形態にしても、生計の維持についても、完全に個人的な独立関係を貫いているし、子の養育に関しても、XY間で子の出生前に養育の負担について合意を取り交すことにより、子との間で個人的な関係を別個に形成することを意図していたものと考えられる。従って、XY間に形成されていた「パートナー婚」と、従来の議論で念頭に置かれてきた「事実婚」との最大の違いは、家族生活を営むための「集団」を形成し、家族の構成員である個人の行動に対し、集団としての制約を加える場合があることを予定しているか否か、という点にあると考えて差し支えない[*52]。そうであるとすれば、XY間での「パートナー婚」が従来の事実婚に関する法的保護の要件に合致していないことは、事実婚に対する法的保護が集団としての家族の秩序形成を基盤としている以上当然であると考えられるし、本件におけるXY間の合意(特に子の養育負担に関する合意)に対して公序良俗違反の疑いがある、との批判が加えられることについても、集団としての家族の秩序維持に合致しない内容の合意であることに対する批判として、明確な説明を加えることが可能となる[*53]。(以上、(2) p.97)
家族に関する論者たちは、女性の社会進出に伴う“家族の多様化” ”ライフスタイルの変化”と大雑把に捉えがちです。しかし、「個人主義」の傾向はその中の一つにしか過ぎません(「個人主義」とは何であるのかをもう少し掘り下げるべきでしょう。しかし、私にはそこまでの能力はないので、一般的な意味での「個人主義」に限定しています)。
そして、こうした「個人主義」者は当然ながら“独身”であることが多いため、「パートナー婚」の実践者はほとんど存在しないように見えますが、「個人主義」の傾向は社会の深層部で進行し、少なくとも願望レベルでは既婚者にも確実に進んでいると思われます。
協調的な行動も、「個人主義」的な行動も、どちらも個々人の欲望のあらわれであると解釈することは可能であり、是か非かで片づける単純な問題ではないはずです。
家族は「集団」なのか
さらに、星野さんは、家族をどこまで「集団」として捉えるかについて言及していて、法律家たちが立場を明確にせずに議論をしている現状を憂えているようにさえ感じられます。
[*21]・・・第二次大戦後における家族法学の最も基本的な観点は、家族法における「個人の尊厳」だったわけであり(我妻栄『親族法』四頁以下(一九六一年))、家族が「集団」であることを正面から肯定する議論は、かかる立場との関係で主張することが事実上困難であったのではないかと思われる。しかしながら、夫婦に対する法的保護を論ずる際の考慮要素として、夫婦として対外的に協同行動をしているか否かを加えることは、夫婦が「一体となって」、すなわち、ある意味での「集団として」行動しているか否かによって判断していることに外ならない。本件のXの行動に対する評価にしても、評価する側がやや無意識的に家族の集団性を前提として議論を展開し、Xの主張の根底にある思想との間で次元のずれが生じている可能性があるのではあるまいか。要するに、徹底された個人主義の下では、現行家族法制度の基本的な部分のうち少なくとも一部はそもそも成り立たない可能性すらあるわけであり、家族をどこまで「集団」として捉えるかについて、立場を明確にしたうえで議論する必要が、今後は強くなるように思われる。((1) p.73)
“主張の根底にある思想” ! やっと理解してくれる人をみつけたと思いました。しかしながら、“本件のXの行動”、“Xの主張の根底にある思想” という表現には正直言って不満が残りました。本件における数々の事実はX1人でつくれるものではありません。XとYの行動であり、Xと(ある時点までの)Yの思想だったはずです。ところで、この場合、XとYは集団ではないのでしょうか。
「複数の集団」に同時に帰属できるのか
おそらく現時点では誰も発想さえできないと思いますが、以下の論点は秀逸です。
[*55] 考えようによっては、XY間の関係は、一方又は双方が別に家族集団の構成員であったとしても、理論的には成り立つ可能性がないではない。この点も、事実婚を含む従来の家族関係が、「複数の集団」に同時に帰属できないことから生ずる破綻状態と、質的に異なりうる部分であると考えられる。((2) p.99)
裁判相手との破局(2001年5月)の後、私は、高校の同窓会で知り合った男性Sと私の家で協同生活(「パートナー婚」)をしていました。Sには妻と3人の子どもがいましたが、知り合った時にはすでにSと妻とは家庭内離婚状態にありました。
協同生活をしている6年間(2003年1月〜2009年2月)、Sの母親の葬儀で顔を合わせた以外は音信不通が続いていたにもかかわらず、Sは妻と子どもたちが住むマンションの住宅ローンを支払い、生活費、学費などを送金していました。家庭内離婚状態の時に、一度Sは妻に離婚を申し出たようですが、妻側からの拒絶に遭ったと聞いています。2009年1月、1番下の子どもも二十歳に達しました。
他人事のように書きました。私にとって重要なのはSとその妻の心が離れているがどうかであって、離婚しているかどうかはまったくどうでもよかったです。むしろ、お金だけでつながった法律婚の在り様を観察することができ、私の理論形成には結構役に立ちました。ただ、「こんなに形骸化した法律婚もあるのに、その法律婚と比較されて私は最高裁で負けたのだな」と、悔しさが込み上げてきたことが何回かあったのは事実です。
このように、「パートナー婚」というものは、たとえ一方が別の家族集団の構成員であったとしても成立するのです。そして、Sとその妻との関係は、戸籍や通帳といった、第三者には見ることができないものによってのみ結ばれている、いわば「秘密婚」といえるのではないですか。星野さんが予見することが現実となっています。
「パートナー婚」とは何か
私とSとの関係について「不倫」と捉える人もいるでしょう。ちょっと複雑に考える人には、私は“Sの家族を経済的に支えた人間”と映るかもしれないし、道徳的な見地からすれば「重婚」にあたるかもしれません。
しかし、私にとってSとの関係は二度目の「パートナー婚」でした。相手が違うので関係性は異なりますが、裁判相手との相違点は、Sとの場合は「同居していた」、Sとの間には「子どもが存在しない」、Sとの場合のほうが「共通の友人が多かった」ことぐらいです。一方、他人には見えない深い部分については、正直言うと、私の人生を心から応援してくれたのは裁判相手のほうだったと思います。このことは、今振り返ってみて初めて実感できることです。
私は、この二度目の「パートナー婚」であるSとの関係と、一度目の「パートナー婚」である本件とを比較してみることを法律家の方々に提案したいです。私という同じ女性が両方の事例の当事者なのですから、仮説も立てやすく、他人にわかり得る浅い部分、「事実認定」を比較・検証するだけで十分に有益であるからです。半世紀ほど前の事例を持ち出して考察している場合ではないと思います。
「パートナー婚」と「不倫」との違いは
2009年2月、Sは、私の家を退去した5日後に高校同期女性である専業主婦(別の男性と法律婚中)と親しくなり、それぞれが自身の法律婚を解消しようと努力することなく、そのわずか半月後にはそれぞれの友人たちに「結婚宣言」をしました。
あれから半年、彼らの現状を私は知りませんが、Sは、私との場合と違って、「複数の集団」に同時に帰属できないということに気づいたのではないかと思います。つまり、それぞれの古い法律婚を壊して新しい法律婚をするか、一方あるいは双方の帰属集団を壊すことができずに「結婚宣言」だけで終わってしまうか、おそらくそのいずれかになるということです。
彼らの一方あるいは双方が帰属集団の構成員のまま、もし彼らが今後も交際を続けるのならば、法律家たちは彼らの関係をどのように判断するのでしょう。
一方あるいは双方の古い法律婚が継続しているのですから、「不倫」ですか。
古い法律婚は実質破綻しているのですから、「内縁」ですか。
何年か経過すれば、「不倫」から「内縁」へ“ラベル替え” ですか。
専業主婦である相手の女性には経済力はありませんので、Sとその女性との関係は「パートナー婚」ではないと思われますが、もし、仮に自身に経済力はなくても、十分な資産があり、Sに頼る必要がなく互いに経済的に独立することができるならば、「パートナー婚」でしょうか。
これらを分析することによって、「パートナー婚」の本質が見えてくるに違いありません。
「共有財産」を築かない男女の同居は可能
2009年2月、Sが私の家を退去するにあたって、その2年前にSが購入し、共同使用していた複合機に関してのみ、どちらが引き取るかで争いが起きました。私はこの複合機を「共有財産」とは認識していなかったため、Sに対して使用料として月々2000円ずつ支払っていました。
本来ならば、Sの所有物はSとともに持ち出されるべきなのでしょう。しかし、私のピアノ教室の講師たちもこの複合機を使用していることなどから、ある金額を提示して、私がこの複合機を引き取ることになりました。
「共有財産」をつくらないことを信条にしてきた私にとって、共同使用していたために起こったこの争いは大変不本意なものでしたが、少なくとも、たとえ男女が同居し、協同で生活していたとしても、「共有財産」をもたない関係の形成は“不可能ではない”ということを明らかにできたと思います。(ちなみに現在Sが住宅ローンを払い続けるマンションは、SとSの妻との共同名義であり、したがって2人の「共有財産」です。)
まとめ
星野さんが提起する内容は、以下の4点に要約することができます。男女関係の破綻に関して、従来の判例法理との整合性だけに意識を向け、法律婚との距離を測定することで事実婚の在り様を判断している法律家の方々! 一度大きく深呼吸して、星野さんの論文を精読していただきたいです。この論考を理解できないのは、家族という集団の恩恵に浴している既婚者たちと、無条件に結婚に憧れている若い人たちだけであると思います。
- 法律婚の法的保護がなぜ必要であるのか、果たして法律婚のどの要素が最も法的保護にとって重要な本質部分であるか、かかる本質部分に対してなぜ国家が法律上の保護を与えてまで関係を維持、存続させる必要があるのか。
- 本件でのパートナー関係は当事者の合意のみを中核とするものであり、憲法第24条における「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとの文言に反するどころか、むしろ合致しているのではないか。
- 本件の各審級における慰謝料請求に対する判断の違いは、XYの関係破綻についての理論的把握の仕方に基づくものであり、単なる妥当不当、賛成反対で片付けてしまうべきものではない。
- 本件のような事案を契機として、改めて家族関係における個人性と集団性とを議論し直し、関係破綻に際しての法律上の保護のあり方を再検討することが、家族法学に与えられた今後の課題である。
(2009年8月30日)