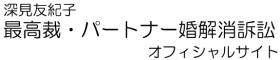「毎日新聞の解説」に対する私のコメント
毎日新聞の記者小林直さんの解説、「契約の有無」についてコメントする前に、この裁判の過程をもう一度振り返ることにします。
私が代理人である弁護士に初めて相談に行ったのは、相手が関係の解消を申し出た日から一ヵ月半ほど経った、2001年6月の半ばでした。弁護士は、「賠償金を取りたいですか。男女のパートナー関係というものを世の中に問いたいですか。」と私に尋ねました。話し合う余地を与えることなく、私との関係を突然一方的に解消するという相手の態度に非常に憤りを感じていた感じていた私は、「賠償金を取りたいです。」と答えました(私が提訴した理由 参照)。社会のためにやっているという気持ちが大きい音楽教育の仕事と違って、パートナー婚という生活形態は自分のためにやってきたからです。社会に対してアピールしたいという気持ちはその頃ほとんどありませんでした。
東京高裁は、「婚姻届を提出せず、法律婚としての法の保護を受けることを拒否し、互いの同居義務、扶助義務も否定するという、通常の婚姻ないし内縁関係の実質を欠くものであったことが認められる。」と準婚関係を否定しながらも、「両者が知り合った昭和60年から平成13年に至るまでの約16年間にわたり、上記関係を継続してきたものであり、・・・互いに生活上の「特別の他人」としての立場を保持してきたこと」を認め、「格別の話合いもなく、平成13年5月2日に突然上記の関係を一方的に破棄し、それを破綻させるに至ったことについては、控訴人(私)における関係継続についての期待を一方的に裏切るものであって、相当とは認め難いものといわざるを得ない。」としました。そして、「被控訴人(相手)は、控訴人(私)に対し、その点における不法行為責任を免れ難いと解するのが相当である。」と判断したのです。
最高裁は、準婚関係を否定すると同時に、「その一方が相手方に無断で相手方以外の者と婚姻をするなどして上記の関係から離脱してはならない旨の関係存続に関する合意がされた形跡はない」とし、「上告人(相手)の被上告人(私)に対する不法行為責任を肯定し、被上告人(私)の請求の一部を認容した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」としました。
もし、東京高裁の「関係継続の期待を一方的に裏切るものである」という記述がなければ、最高裁は単に準婚関係を否定するだけに止まり、おそらく「関係存続に関する合意がされた形跡はない」という記述は出てこなかったでしょう。つまり、最高裁のこの記述は、東京高裁の記述に導き出されたのです。
さて、次の文章が、判決当日に書かれた小林直さんの解説です。
男女のパートナー関係を巡る18日の最高裁判決は、2人が互いに束縛し合わない間柄だったことを「関係存続に関する合意(契約)がなかった」と判断して、関係解消における賠償義務を否定した。従来の男女関係を巡る訴訟では、正式な婚姻関係に近ければ賠償義務を認め、そうでなければ退ける司法判断が多く、専門家から「(夫婦か否かという)身分関係に重点を置き過ぎている」との批判があった。今回の判決はこうした視点を持ち出さず、男女関係を一種の「契約」と位置づけており、新しい関係に新しい視点で応えたものと言えるだろう。
婚姻届は出していないが、婚姻の実態がある「内縁関係」を巡っては、大審院が1915年1月、「正当な理由無く破棄すれば賠償請求の対象となる」とする判断を示し、戦後も最高裁が「結婚に準じた関係(準婚関係)」と位置づけて同様の判断を示してきた。
内縁関係にあるかどうかは▽共同生活の有無▽家計の同一性▽子供の共同養育−−などの要素を総合的に考慮して判断される。しかし、今回のケースはどの要素も満たさず、内縁関係には当たらないため、判断が注目された。
今回の判決は準婚関係という従来の議論については「(準婚関係と)同様の保障を認める余地はない」と言及しただけにとどめ、2人の関係を詳細に検討したうえで、それが「関係存続の契約」と言えるかどうか、という視点から結論を導いた。外見上は今回と同じでも、2人の仲が永続的に続くことを約束(契約)していれば、逆の結論になることも予想され、どんな場合でもパートナー関係の解消は自由−−と受け止めるのは早計だろう。
「外見上は同じでも、2人の仲が永続的に続くことを約束(契約)していれば、逆の結論になることも予想される。」ということは、「我々は婚姻届を出さないが、永続的な関係であるという合意をし、ここに契約を結ぶ」というような文面を取り交わしていたならば私の勝訴となった可能性が高いということでしょう。つまり、「関係継続に関する合意を残しておけば相手に無断で2人の関係を破棄できない」ということを意味しているのではないですか。
届を出さない=国家に管理されない関係を選ぶのならば、国家をあてにせず、自分たちで管理すべきであるというのはある意味では当然のことかもしれません。しかし、弁護士などの法律家はこれまでそのようにアドバイスしてきたでしょうか。日本の多くの事実婚カップルのうち、両者間で何らかの取り決めをしている人たちはほとんどいないのではないでしょうか。正式な婚姻関係に近いということをアピールすることによって、契約がないという弱点を補おうとしてきたのではありませんか。
この事件の概要を読んで、「この男女は別居で別経済だし、内縁や事実婚にはあたらないので、一方的に関係を破棄されても仕方がない。自分たちには夫婦としての実態があるから大丈夫」と安堵している事実婚カップルも多いと思いますが、“内縁にもあたらない”とされるこの事件が、地裁×、高裁○、最高裁×というところまで来たことこそが重要だと思います。この事件の判決が与えるであろう影響は、正当な事実婚、異端な事実婚といった比較をはるかに超えるものです。国家に管理されることなく、それぞれに契約を交わすことによって相手の不当な行為に対して防衛するという、目の覚めるような方法を最高裁が提案したとも読み取れるからです。
さて、次に挙げるものが、私と相手が法律婚をするのを取りやめて、「特別の他人」としての関係を持つことを表明した葉書(乙4号証)です。1986年春、私の関係者には相手が、相手の関係者には私が送付しました。“冷めないスープ”を表すイラストがまるで“冷めたラーメン”のようだったので、東京芸大の油の大学院を出ていてもこの程度なのだなと失望したのを憶えています。裁判のなかで、相手はこの葉書を“婚約解消”の証拠として出し、私からの脅迫によって送付することになったと述べていますが、校正刷りに修正を加えているのは相手です。
この文面を見ながら、関係継続に関する合意を裁判所に納得させることができる文面とはどういうものかを考えてみてください。
「関係を解消してはならない」「他の人と結婚しない」と書くのか。関係解消の際の取り決めを書けばいいのか。文章で残すという方法しかないのでしょうか。インターネットの書き込みに、一方的に破綻を申し出たほうが「100万円×継続年数」の賠償金を支払うといいといった意見もありましたが、これも契約の1つかもしれません。しかし、将来のことは誰にもわからず、大金持ちから無一文に転落することもまたその反対もありだとすれば、契約を結んだときに契約破棄の際の収拾の内容について書くことは不可能ではないでしょうか。法律婚の破綻の際の慰謝料問題同様に、“ない袖は振れない”ですから。「一方的に破棄することはできない。破棄する際は収拾について協議する」というぐらいの文面が現実的だと思います。
さて、このサイトで何度か引用している2001年5月2日付けの私宛の相手の手紙。これはどうみても関係破棄の通告です。そうであるとすれば、少なくともその手紙を書く前までは関係継続の意思を持っていたはずなのですが、相手は、前述の葉書を出した1986年の時点で両者は関係を終了させていて、その後16年間に起こった出産や仕事の協力などのあらゆる事柄においてはその都度契約を交わし、そしてその都度完了させたのだから、永続的な信頼関係はまったくなかったという主張に終始したのです。
男女関係が多様化するなかで、両者の関係を客観的に判断することは現状でも困難ですし、今後ますます難しくなっていくでしょう。それにしても、毎日新聞の小林さんが提示した1915年の判例は古すぎませんか。戦前の旧民法下の、女にはまだ選挙権もなかった時代の例を持ち出すなんて、滑稽でさえあります。判決の翌日、「たとえ別居で別経済でも深見さんが子どもを育てていたら反対の判決になっていたと思いますよ。」と私の代理人が言ったとき、子どもを相手側が育てるというのが我々の契約だったのにと納得のいかない気持ちになりました。
私と相手の間には別れるときはどうするという契約がなかったために私は敗訴しましたが、これから事実婚を選ぼうとしている人に「契約」について考えてもらう契機となる裁判を起こしたことに関してまったく後悔はありません。心からやってよかったと思っています。法律婚夫婦の場合、関係存続に関する合意は婚姻届で証明することができますが、婚姻届を出していない男女の場合は、その婚姻届が存在しないため、彼らの生活の実態で婚姻に準ずる関係であるかどうかを他人に推測させるしかなかったのですから、一歩も二歩も前進でしょう。
東京高裁の判決によって導かれた今回の最高裁の判決は、公序良俗に反しない限り、男女の社会通念を持ち出さずに当事者同士の約束が認められるという、新しい方向性を打ち出したと捉えることができると思います。そして、「関係存続に関する合意」は、子どもがいることや、誰が育てるか、別居が別経済かなどとは本来無関係に、当事者同士によってなされるものだと思います。
日本は「なあなあ、あ、うん」の社会であり、日本人には揉め事が生じてから対処するという習性がありました。子供の養育について、私と相手が公正証書に書き残したことを尋常の沙汰ではないと批判している人も多かったのに、一転、日本は男女の関係について契約国家になっていくのかもしれません。
現在、男女の両方がある一定額以上の収入を持ち、かつ2人の間に子どもが存在せず、相手側の資産を自分のものにしたいというような欲がなければ、婚姻届を出すメリットなど見当たりません。さらに、「関係存続に関する合意」さえしておけば、法律婚と比べても何ら不便や損失はないと思います。旧姓を通称として使用するなどという面倒くさいことをしてまで婚姻届を出す意味などどこかにぶっ飛んでしまいそうです。