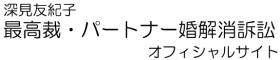「パートナー婚解消訴訟」は、提訴より約2年11ヶ月の歳月を経て、2004年11月18日、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)で決着がつき、原告である私(深見友紀子)の敗訴という結果になりました。TV、新聞など多くのメディアが本件を取り上げましたが、その内容には数々の誤解や間違いが含まれていましたので、同年11月21日、私はこのサイトを立ち上げることにしました。本件は一パートナー婚の破綻という個人的な問題だけに止まらず、男女関係の多様化、女性の就労、出産・育児など、現代社会における諸問題に密接に結びついており、本件に関心のある方々に向けて私自身の言葉や正確な資料を提供したいと考えたからです。
判決直後から翌2005年夏にかけて、法律家4氏(水野紀子(東北大学大学院法学研究科教授、石川博康(学習院大学法学部助教授)、良永和隆(専修大学法科大学院教授)、本山敦(立命館大学法学部助教授) ) による本件の解説および判例解釈が出ましたが、従来の法律外男女関係の判例と比較しつつ、本最高裁判決を肯定するものであり、その結果、本最高裁判決は、男女関係が破綻した場合における“法的保護の限界事例”として位置づけられました。私が最も不本意だったのは、本件の高裁、最高裁の判決文の字面だけを読んで解説をつくるという、上記の4氏をはじめとする法律家の安易なやり方でした。
民事訴訟、とりわけ家族内の紛争は高度なプライバシーに触れるので、当事者からコメントが出ることはほとんどありません。そのため、ある事例の原告をX、被告をYなどと表記し、定型化して解説するというやり方がまかり通ってきました。家族法の研究者たちは、原告である私自らがサイトを開き、情報を公開していることを知って少々驚いたに違いありません。その後に出た論考には、このサイトを参照しなければ知り得ない事柄が散見されるようになりました。
2009年9月、私は、星野豊氏(筑波大学社会・国際学群准教授)が2006年3月に発表した「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(1)」 「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(2・完)」(筑波法政)に対し、詳しいコメントを書きました。しかし、本業を持ち、雑務に追われる私は、当時次々に出てきた他の論考類にコメントをすることもなく、数年が過ぎました。
そんな折、チャンスがやってきました。私に1年間の休暇(2012年4月1日から本日まで)がもたらされたのです。1年の間にこれらの論考類にコメントし、未公開の書類を公開しよう。私はそう決めて、このサイトでも予告したのですが、実際はまったく熱が入らず、作業が進みませんでした。
理由は2つありました。
1つは、本件以降、同様の判例が出ないため、注目度が低いこと。
もう1つは、被告が変貌したことでした。地裁から最高裁まで弁護士を立てない“本人訴訟”で闘ったほど、対抗するエネルギーに溢れていた被告が、自身のすべてを賭けて作った文庫の活動を、本最高裁判決後に実質休止し(被告の妻のmixiより)、美術とはまったく関係のない職に就いていること(娘より)など。本業以外のことにエネルギーを注ぐと、職業人としての意欲や実力が削がれるかもしれないという恐怖心が頭をもたげました。
「有言実行」という意味もあり、また、以下の21ケの書面をテキストファイルにしてくださった方への恩義もありましたが、仕事上の意欲や実力が削がれるかもしれないという恐怖心には勝てず、1)2)のうち、訴状を公開しただけで、また3年の月日が流れてしまいました。
1) すでに公開している判決文(東京地裁、東京高裁、最高裁)、最高裁上告関連書類に加え、訴状以下、原告および被告が裁判所へ提出したすべての書面(21書面)を公開する。
2) 併せて、1)のテキスト版を公開し、原告および被告が裁判所へ提出した資料などにリンクさせることにより、よりリアルに本件が理解できるようにする。
そんな折、2015年の終わり、被告の妻が癌で亡くなりました(享年47)。そのことが契機となって、本件の事実を残しておきたいという気持ちが少しだけ復活しています。ちなみに裁判相手との破局(2001年5月)の後、私の家で協同生活(「パートナー婚」(2003年1月〜2009年1月)をしていた男性Sも、ほぼ同じ頃、肝臓病で亡くなりました(享年59)。
これから私が公開していく上記の書面を読み進めるならば、私との間に2人の子どもが存在する被告が、「16年間に及び、原告(私)に脅迫され、忍従の関係を余儀なくされてきた」という主張を繰り返したことがわかるでしょう。そして、東京高裁の裁判長が被告の執拗な主張に辟易としたことが、東京高裁判決に大きく影響しています。また、最高裁においても、もし私が2人の子どものうち1人でも育てていたら、私が勝っていただろうことなどが読み解けると思います。これまで本件の判決について、東京高裁=革新、最高裁=保守という図式で語られてきましたが、決して高裁=革新ではありません。
本件における親子の関係性については、「子どもを巻き込んでかわいそうだ」というのが一般的な見解でしたが、係争していた頃から、約13年の歳月が流れました。娘が、被告である父親に内緒で、母親である私の家(東京都新宿区)で暮らし、その後独立して3年が経ちました。また、息子も先月23歳になり、本件の関係者はもう大人ばかりです。
20数年前、大学を入り直したために学部卒業時にすでに29歳になっていた私は、「相手側に育ててもらうということ」=「自分では育てない」という条件で、32歳、35歳のときに子どもを産みました。当時、私には会社員や公務員のような定収入も、出産休暇、育児休業保障もなく、両方の祖父母も近くに住んでいませんでした。「深見さんならもし仕事と育児を両立していても、今と同じポジションを得ることができたかもしれない」という人がいるかもしれません。しかし、“もし、あの時・・”と振り返っても仕方がありません。その時その時で最善を尽くすしかない。多くの方々からバッシングを受けましたが、私には後悔はありません。
結婚する、結婚しない、結婚して子どもを持つ、結婚して子どもを持たない、結婚しないで子どもを持つなど、さまざまな選択がありますが、結婚せずに子どもを産んでパートナー(側)に育ててもらうという選択があってもいいと思います。もし私が常識的な行動をしていたとしたら、おそらく私には子どもがいなかったでしょう。でも、私には子どもたちがいるのですから、私の選択に少子化を食い止めるヒントがあるかもしれません。
2016年3月21日
深見友紀子